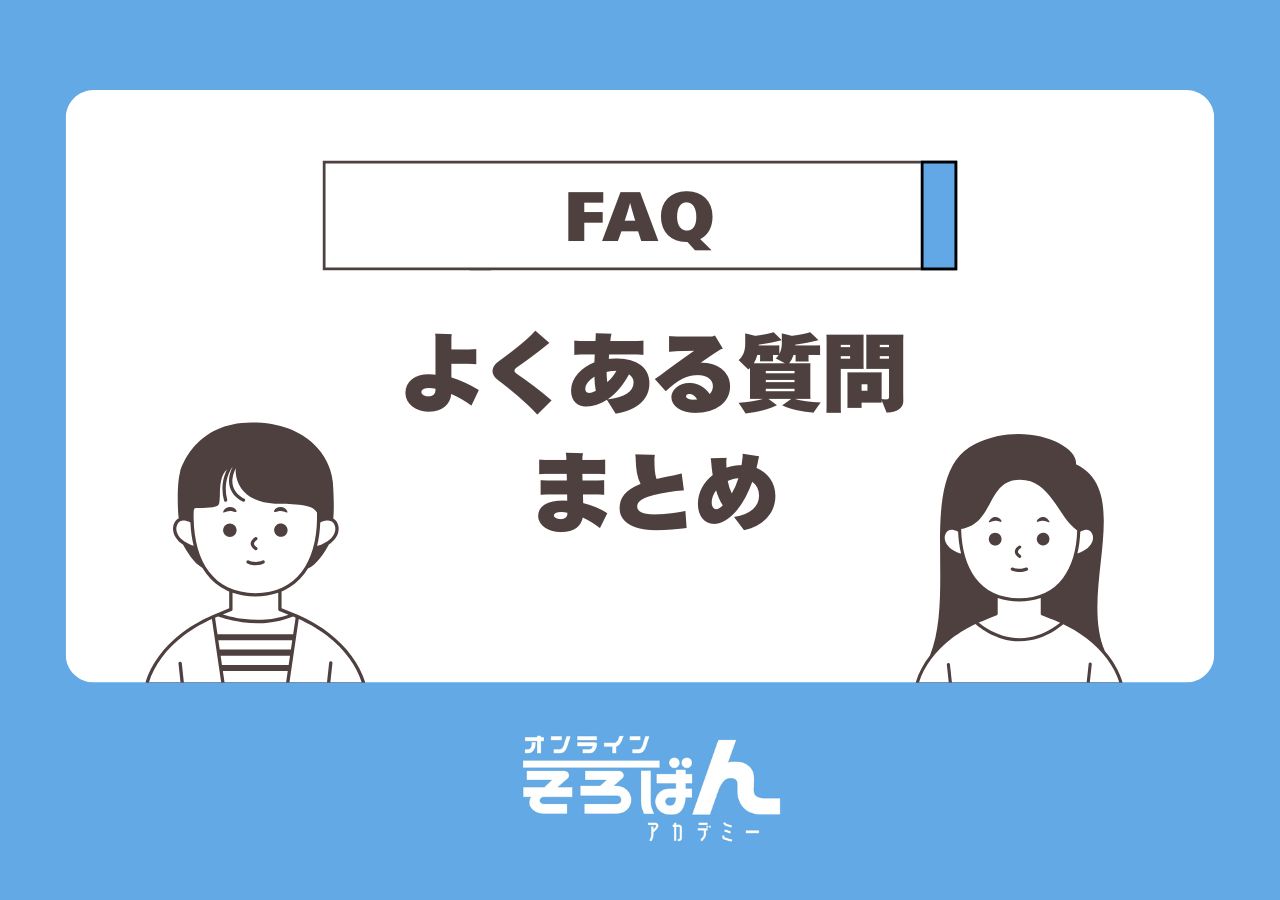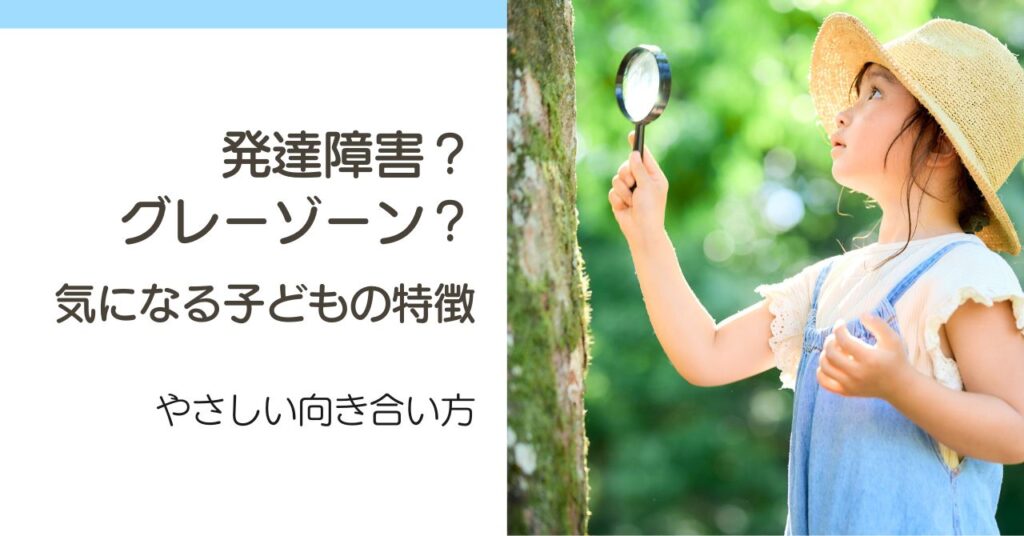
うちの子、ちょっとまわりと違うかも…

ちょっとした違和感から、「発達障害」や「グレーゾーン」といった言葉を検索された方も多いのではないでしょうか。
発達障害は診断で明らかになりますが、その前に「育てにくさ」や「うまく言えない不安」を感じることもよくあります。
最近では、診断がつかなくても困りごとを抱える“グレーゾーン”の子も増え、どう向き合えばいいのか迷う場面も増えています。
をわかりやすく整理しつつ、
“得意”や“伸びる力”に目を向けるヒントもご紹介します。

診断をすすめるのではなく、お子さんとどう関わるかを一緒に考えるための記事ですので、少しでもモヤモヤしている方に、気づきの“きっかけ”になれば幸いです。
↓好きな所だけ選んで読めます↓
発達障害?グレーゾーン?と思ったら
発達障害という言葉の意味や、最近よく聞く“グレーゾーン”という考え方を理解することで、子どもの行動が少し違って見えてくることもあります。
ここでは、診断前に知っておきたい基礎知識と、子どもの「気になる行動」とどう向き合っていくかのヒントをやさしく整理していきます。
発達障害の診断前に知っておきたい基本
「発達障害」という言葉を聞くと、どこか遠い存在のように感じるかもしれません。
でも、子育ての中で「うちの子、ちょっとほかの子と違うかも?」と感じたことがある方にとっては、身近なテーマにもなり得ます。
発達障害は、大きく分けると以下の3つのタイプに分けられます。
| タイプ | 主な特徴 | よく見られる行動例 |
|---|---|---|
| ASD (自閉スペクトラム症) |
相手の表情や態度などより、文字や図形、物の方に関心が強い。 見通しの立たない状況では不安が強いが、見通しが立つ時はきっちりしている。 |
「目を合わせない」 「急な変化にパニック」など |
| ADHD (注意欠如・多動症) |
次々と周囲のものに関心を持ち、周囲のペースよりも エネルギッシュに様々なことに取り組むことが多い。 |
「じっとしていられない」 「話を最後まで聞けない」など |
| LD (学習障害) |
「話す」「理解」は普通にできるのに、「読む」「書く」「計算する」ことが、 努力しているのに極端に苦手。 |
「文字が左右反転する」 「九九が覚えられない」など |
どれも脳の発達や情報処理の仕方に特徴がある状態で、「育て方のせい」や「親の努力不足」では決してありません。
ただし、発達障害は外見ではわかりづらく、診断には医師による総合的な評価が必要です。
家庭で「もしかして…」と感じた時点では、まだ確定ではないからこそ、焦らずに情報を整理していくことが大切です。
グレーゾーンってどんな子?
最近よく聞く「グレーゾーン」という言葉。
これは、発達障害とまでは診断されないけれど、日常生活や集団生活の中で“ちょっと困りごと”がある子を指すときによく使われます。
たとえば、
など、一見すると「その子の個性かな?」とも思えるような特徴ですが、
本人にとっては日々の生活で苦しさやストレスを感じていることもあります。
グレーゾーンの子どもは、診断の基準をすべて満たさないため、公的な支援につながらないこともあります。
けれど、まわりの理解やちょっとした工夫があるだけで、毎日の過ごしやすさは大きく変わることも。
気になる行動だけで決めつけない
「発達障害かも」「グレーゾーンかも」と感じるのは、親として自然なことです。
でも、そこですぐに「この子は〇〇だから」と決めつけてしまうことは、子どもにとっても親にとっても負担になりかねません。
子どもは成長とともに行動が変わることも多く、環境や関わり方によって落ち着いてくることもよくあります。
逆に、過剰に心配しすぎると、子どもの可能性を狭めてしまうことにもつながる。
大切なのは、
- 「なぜこんな行動をするのか?」と背景に目を向けること
- 子どもが何に困っているのかを理解しようとすること
- 必要に応じて、専門家の手を借りる準備をしておくこと
「気になる行動」は、その子が何かを伝えようとしているサインかもしれません。
だからこそ、“判断”よりもまず“観察”から。
親御さん自身が不安になりすぎず、ゆっくり向き合っていくことが大切です。
子どもに見られる「気になる特徴」は?
子どもと関わる中で、「ちょっと気になるな…」と思う行動が出てくることがあります。
それがすぐに“発達障害”と結びつくわけではありませんが、少し注意して見ていくことで、子どもにとっての困りごとが見えてくることもあります。
ここでは、よくある特徴や、それが“個性”との違いなのかどうかを、一緒に考えてみましょう。
よくある傾向や行動例
発達障害やグレーゾーンの子どもに見られる行動には、次のようなものがあります。
- 落ち着きがない(多動)
→ じっと座っていられず、教室でも立ち歩いてしまう - 話を最後まで聞けない
→ 会話を途中でさえぎったり、急に違う話をする - 強いこだわりがある
→ 同じ服しか着たがらない、順番が少し違うと怒る - 空気が読みにくい
→ 人との距離感が近すぎたり、冗談が通じにくい - 感覚が敏感すぎる/鈍感すぎる
→ 音や光にすごく反応したり、痛みに気づきにくかったりする
これらの行動は「わがまま」や「甘え」ではなく、本人もどうしていいかわからないまま困っていることも多いのです。
個性との違いってどこ?
子どもにはそれぞれの性格やクセがあります。
では、どこからが「個性」で、どこからが「支援が必要な特徴」なのでしょうか?
一つの目安として考えられるのは、「生活や集団の中で困っているかどうか」です。
例えば
- 家では元気いっぱいだけど、保育園や学校では問題なく過ごせている
→ この場合は「その子の個性」と考えられることが多いです。 - 家でも学校でも、同じことでトラブルが起きたり、本人がつらそうにしている
→ この場合は、少しサポートがあった方がいいかもしれません。
また、「親が困っている」という視点だけでなく、「子ども自身が困っているか」という視点も大切です。

子どもが自信をなくしていたり、毎日が苦しそうに見えるときは、支援や理解が必要なサインかもしれません。
「特徴」は子どもからのサイン
子どもに見られる「気になる特徴」は、その子が何かを伝えようとしているサインかもしれません。
言葉でうまく伝えられない分、行動として現れていることもあります。
たとえば
- かんしゃくを起こす → 実は環境の変化が不安だった
- 集中できない → 興味がわかない内容で、頭がいっぱいだった
- こだわりが強い → 自分の安心できる世界を守っている
こうした行動を見たとき、「これはダメ」とただ直そうとするのではなく、「なぜそうしているのかな?」と背景に目を向けてみることが、子どもとの関係を深めるきっかけになります。
困った行動の“裏側”には、子どもなりの理由や気持ちがあるものです。

そのサインを見逃さず、少しずつ理解していくことが、やさしい向き合い方の第一歩になります。
診断を受ける?どこに相談すればいい?
子どもの行動に気になるところがあっても、「すぐに病院に行くべき?」「様子を見たほうがいい?」と迷う親御さんは多いと思います。
ここでは、相談するタイミングや場所、診断についての考え方を、やさしく整理していきます。
専門家に相談する目安とは
まず、「相談してみようかな?」と迷ったときは、次のような視点を持ってみてください。
- 家でも園や学校でも、似たような困りごとが続いている
- 子どもが毎日ストレスを感じているように見える
- 家族の中でも、子どもとの関わりに疲れを感じている
- 周りの子との違いに戸惑い、どう接していいか分からない
これらが続くようなら、「ちょっと相談してみようかな」という気持ちで専門家に話してみるのも一つの方法です。
「すぐに診断されるのでは?」と心配になるかもしれませんが、多くの場所では、まずは数回に分けて相談をするところから。
必要があれば、次のステップにつなげてくれます。
相談できる場所や窓口
相談できる場所は、意外とたくさんあります。
最初は身近なところからで大丈夫です。
- 地域の保健センターや子育て支援センター
→ 発達相談を受けつけているところも多く、無料で対応してくれる場合もあります。 - 小児科やかかりつけ医
→ 気になる行動を伝えることで、発達専門の機関を紹介してもらえることがあります。 - 発達外来や児童精神科
→ より専門的な検査や診断ができる医療機関です。予約が必要なことが多いです。 - 保育園や幼稚園、学校の先生やスクールカウンセラー
→ 日常の様子をよく知っている人たちだからこそ、気づいてくれることがあります。
「どこに行けばいいかわからない…」という場合は、まずは保健センターや園・学校に相談してみるとスムーズです。
診断を受けても受けなくても大切にしたい視点
診断を受けるかどうかは、親として悩むところです。
「診断がつくとレッテルを貼られるのでは?」と感じる方もいれば、「早めにわかったほうがいい」と考える方もいます。
どちらが正しいということではありません。
大切なのは、診断が“ゴール”ではなく“きっかけ”になることがある、ということです。
診断を受けることで、
- どんな配慮があれば子どもが楽に過ごせるかが見えてくる
- 学校や周囲に理解を得やすくなる
- 親が「ひとりじゃない」と感じられることもある
一方で、診断がなくても、その子に合った接し方を工夫することは十分にできます。

一番大切なのは、「その子にとって過ごしやすい環境は何か?」を考えること。
それは診断の有無に関係なく、親子でできることです。
家庭でできる、子どもとの接し方
ちょっとした考え方の工夫や関わり方を変えるだけでも、子どもとの関係がぐっとやわらかくなることがあります。
ここでは、家庭の中でできる、やさしい向き合い方のヒントを3つご紹介します
叱るより、まず“観察”してみる
何度言っても直らない…

子どもが困った行動をしたとき、つい叱ってしまうことはありませんか?
そんなときは、叱る前に「なぜこの行動が出ているのか?」を観察してみることがとても大切です。
たとえば、
- 集中できないのは…
▶「静かすぎて不安」なのかも - おもちゃを片づけられないのは
▶「順番の理解が難しい」のかも - 友だちにきつい言い方をしてしまうのは
▶「自分の気持ちを言葉にできない」からかも
こうした背景は、叱るだけでは見えてきません。

「いつ・どこで・どんなときに」そうした行動が起こるのかを記録してみることで、子どもなりのパターンや理由が少しずつ見えてくることもあります。
責めない前向きな声かけ
子どもがうまくできないとき、
「なんでそんなこともできないの?」とつい言いたくなることもあるかもしれません。
でもこの言葉、子どもにとっては責められているように聞こえてしまうことがあります。
代わりにおすすめしたいのが、こんな声かけです。
こんなふうに声をかけることで、子どもは「自分のペースでやっていいんだ」と安心できます。

できたことを一緒に喜ぶ経験は、子どもの自信や前向きな気持ちを育てることにもつながります。
子どもも困っているかも?と考える
ときどき忘れがちですが、子ども自身も「できない自分」に悩んでいることがあります。
注意されるたびに自信をなくしたり、がんばってもできないことにイライラしてしまうことも。
そんなときこそ、親が「あなたの味方だよ」という姿勢を見せてあげることが大切です。
- がんばってるの、ちゃんと見てるよ
- できないことより、できていることのほうが大事だよ
- 大丈夫、ゆっくりでいいよ
こうした言葉は、子どもの気持ちを落ち着かせ、自分に対して少しずつ前向きな気持ちを持てるようになります。

まずは、味方でいてあげることが一番のサポートになりますよ
子どもの“得意”に目を向けてみよう
発達に特性がある子どもと向き合うとき、実は子どもが“夢中になれること”に注目することも、すごく大切な視点です。
得意なことに出会えた子どもは、生き生きとした表情を見せてくれます。
ここでは、「できない」ではなく、「できるかも」「好きかも」を見つけるヒントをご紹介します。
苦手より“夢中”を大事に
うちの子は◯◯が苦手で…

そんなふうに、苦手なところにばかり目が向いてしまうことって、親なら誰にでもあると思います。
でも実は、「苦手」の裏には、「好き」や「得意」が隠れていることがあります。
たとえば、
- おしゃべりが得意 → 言葉で表現する力がある
- 一つのことにこだわる → 集中力や観察力が高い
- マイペースで動く → 自分の世界を大切にしている
何気ない遊びの中でも、「この子、これ好きそうだな」「時間を忘れてやってるな」と感じることがあれば、それは夢中になれる“ヒント”かもしれません。

「苦手」を直すより、「夢中」を伸ばすほうが、子どもの伸びる力につながるかもしれません。
好きなことなら集中できる子もいる
発達に特性がある子の中には、「興味があることにはびっくりするくらい集中できる」という子が少なくありません。
- 数字や図形が好きで、いつまでもパズルに取り組んでいる
- 絵を描くことが好きで、時間を忘れて描き続ける
- 動きのある遊びやゲームで高い反応を見せる
こうした姿は、その子の「伸びる力」の入り口です。
苦手なことを無理に克服させようとするよりも、得意を軸に自信を育てていくほうが、子ども自身も自然にのびのびできます。

苦手を直すより、夢中になれる“好き”も見つけませんか?
そこに、その子だけのすごい力が眠っているかもしれないよ。
「得意を伸ばす」が子どもをラクにすることもある
苦手を直すより、「好き」「得意」を伸ばす方が、子どもにとっても気持ちがラクになります。
「自分ってこれができるんだ」と感じることは、自信や安心感につながります。
たとえば、
- 「そろばん」で数字が得意な子がぐんぐん計算力を伸ばした
- 「プログラミング」で物をつくる喜びを知った
- 「レゴ」や「ブロック遊び」で創造性を発揮した
こうした経験が、「できる」「たのしい」「もっとやりたい」につながっていくと、少しずつ子ども自身が前向きに動き出してくれることがあります。
大人の私たちも、苦手なことを指摘されるより、得意なことをほめられるほうが嬉しいですよね。
子どもも同じです。

“できる”の感覚を積み重ねていくことが、子どもを支えるやさしい方法になるのですね。
そろばんやプログラミングが向いている?
子どもが「集中して取り組めるもの」を見つけたとき、その表情はとても生き生きしています。
特に、規則性があって、やればやるほど上達が見えるものは、発達に特性がある子にとってハマりやすいことがあります。
ここでは、そろばんやプログラミングといった習い事が、どんな子どもに合いやすいのか、どんなメリットがあるのかをやさしく紹介します。
規則性・集中・達成感が得られる習い事
発達に特性がある子の中には、
- 変化が少ない
- 手順が決まっている
ことに安心感を覚えるタイプの子がいます。
そういった子にとって、そろばんやプログラミングが “自分のペースで取り組める” 安心な学びになることがあります。
そろばん:ルールが明確で、繰り返すほど計算が早くなる。目で見える進歩もわかりやすい。
プログラミング:順番通りに動かす、目的に向かって組み立てる、というルールに安心できる。自分で作ったものが動く喜びも大きい。
どちらも「やればやるほど上手くなる」体験が得られるため、達成感や自己肯定感を育てるきっかけにもなります。
特に、発達に特性のあるお子さんにも理解がある教室であれば、安心して自分のペースで取り組むことができます。
「うちの子、こういうの得意かも」
と感じた方は、まずは気軽に体験してみるのもひとつの方法です。
他にも、発達特性やグレーゾーンの子どもがハマりやすい習い事をまとめた記事がありますので、参考にご覧ください。
▶ グレーゾーンの子どもにハマる習い事5選!集中力と自己肯定感を高める方法
お子さんにとっての“夢中になれる学び”が、きっと見つかるはずです。
子どもの“好き”を見つけるヒント
そろばんやプログラミングが向いているかどうかは、次のような日常の様子から見えてくることがあります。
数字に興味がある・時計やカレンダーが好き
▶ 裏にある特性・傾向
- 抽象的な「数」を具体物として捉えるのが得意
- 時間や順序を構造的に理解する力がある
- ルールや規則性への安心感がある
▶ なぜ向いている?
そろばんやプログラミングは、「順序・数の法則性・計画性」で成り立っており、数字を扱う感覚に親しみがある子にとって、脳に負担が少なく、学習の入り口がスムーズになる。
パズルやブロックなど手を使って作るのが得意
▶ 裏にある特性・傾向
- 空間認知力や論理的思考力が高い
- 試行錯誤するのが苦ではなく、結果が見えると安心するタイプ
- 手と頭を同時に動かすことに快感を覚える傾向
▶ なぜ向いている?
そろばんもプログラミングも、「操作しながら考える」活動。パズルやブロックと同様に、段階的に考え、形を作っていく構造が、遊びの延長として入りやすい。
同じ遊びを繰り返し楽しむことが多い
▶ 裏にある特性・傾向
- 安定感のある行動パターンを好む
- 結果が予測できることに安心しやすい
- 「慣れることで力を発揮する」タイプ
▶ なぜ向いている?
そろばんやプログラミングは、繰り返しが力になる学習。やればやるほど成果が見えるため、「同じことを繰り返しても飽きない」タイプの子はどんどん吸収しやすい。
決まった手順を好み、マイルールがある
▶ 裏にある特性・傾向
- 自分の中で世界を構築して安心する傾向
- 流れや手順が明確だと、混乱せず安心して取り組める
- 計画的な処理が得意で、ルール違反には強いストレスを感じることも
▶ なぜ向いている?
そろばんもプログラミングも、「決められた手順」を積み重ねていく活動。手順が明確で、毎回やり方が変わらないので、自分のルールや手順がある子にとって居心地のよい学習体験になりやすい。
こうした日常の中に見える“ちょっとした傾向”は、実はお子さんの「どんな学び方が合うか」のヒントになります。
無理に合わせるのではなく、得意な脳の使い方にフィットした習い事を選ぶことで、学ぶ楽しさも自然に育っていきます。

いくつか体験してみて、子どもの反応を見ることがいちばんの近道です。
「できた!」を育てる習い事
子どもにとって「できた!」という経験は、何よりも自信になります。
特に、発達に特性があって、
- 失敗体験が多い
- 叱られることが多い
と感じている子には、成功体験がとても大きな力になります。
習い事の中で、
- 前より早く計算できた!
- 自分でプログラムを完成できた!
- 褒められた!
そんな経験が積み重なることで、自分にもできることがあるんだ、という感覚が育ちます。
そろばんやプログラミングは、特別な才能がなくても始めやすく、少しずつ進歩を実感しやすい習い事です。

「できた!」って、子どもにとっては魔法の言葉。
楽しさと成功体験が、ぐんぐん伸びる力につながっていきますよ。
まとめ|「らしさ」を大事にしたい子育て
発達障害やグレーゾーンの子には、行動や感じ方に特徴があります。
でもそれは「困ったこと」ではなく、その子なりのサインと受け止めることが大切です。
まずは叱るより、よく観察すること。
「なぜできないか」より「どうすればできるか」を一緒に考えると、子どもとの関係がやわらかくなります。
苦手よりも、「好き」「得意」を見つけてあげると、自信ややる気につながります。
そろばんやプログラミングは、ルールがわかりやすく、達成感を得やすい習い事。
「できた!」という経験を積み重ねる中で、得意を伸ばすきっかけにもなります。
「うちの子、これ好きかも」と感じた方は、
まずは無料体験から始めてみるのもおすすめ。
✅️ そろばん教室を探すなら
オンラインそろばん教室のおすすめ10選
年長〜小学生向け【最新版】
✅️ プログラミング教室なら

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が、少しでもあなたとお子さんの毎日をやさしく照らすきっかけになりますように。