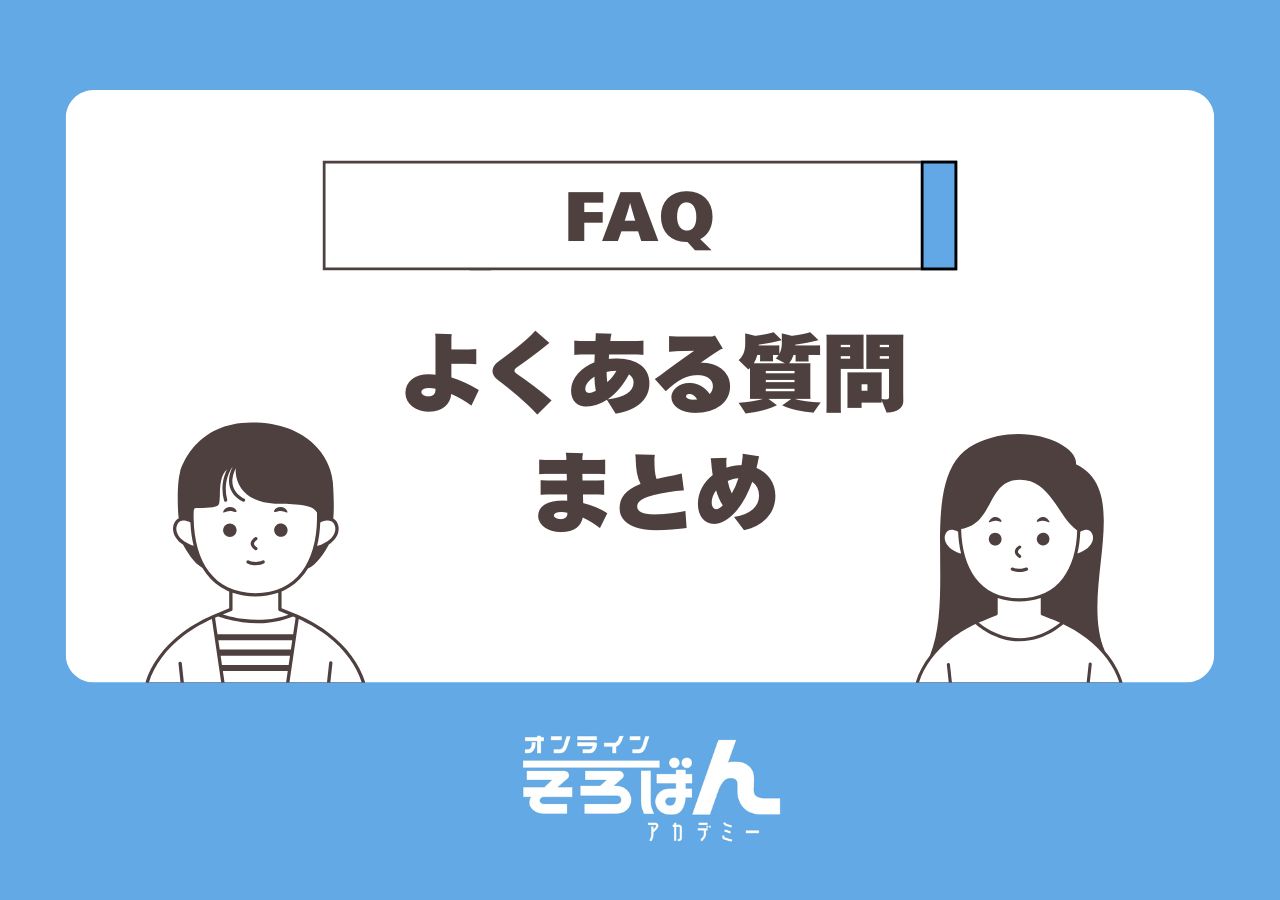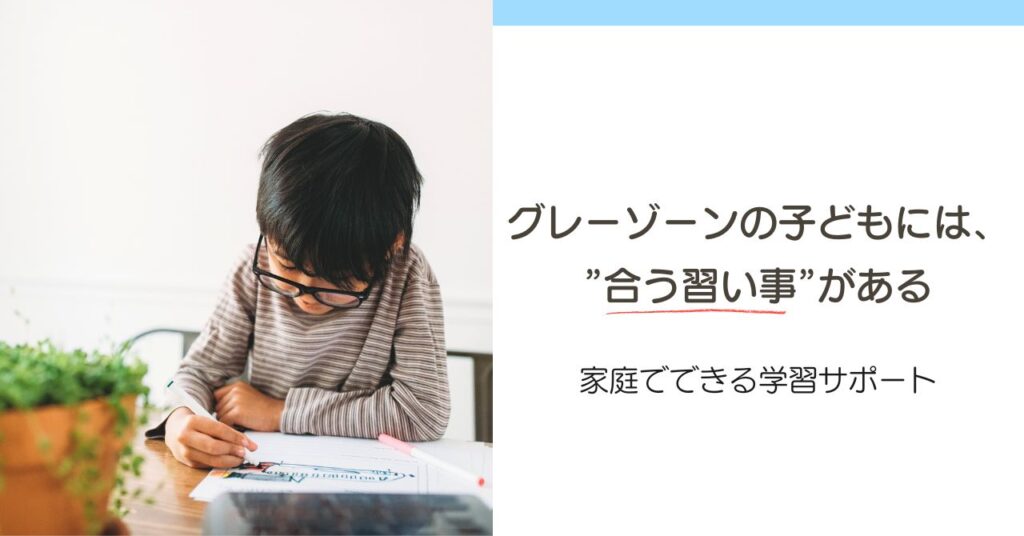
うちの子、勉強になると集中できない

教えてもすぐ忘れてしまう


そんな悩みを感じて、もしかして発達障害やグレーゾーンかも…と検索された方もいるのではないでしょうか。
でも、勉強がうまくいかないのは、「やる気がないから」でも「能力が足りないから」でもありません。
実は、学び方さえ合えば、発達障害やグレーゾーンと思われる子どもでもぐんぐん伸びることがあります。
この記事では、
- 発達障害やグレーゾーンの子どもに合う勉強とはどんなものか?
- なぜそれが合うのか?
- 家庭や学校でできるサポート方法は?
という流れで、わかりやすく解説していきます。
まずは、「どんな勉強なら合いやすいのか?」という疑問に、先にお答えしましょう。
↓好きな所だけ選んで読めます↓
発達障害やグレーゾーンの子どもに習い事と学び方
ではさっそく本題です。
発達障害やグレーゾーンの子どもに合いやすい習い事とは、どんなものなのでしょうか?
実際の家庭や専門家の声などから、「そろばん」と「プログラミング学習」の2つはとても相性がよいという見えてきました。
※教育複合施設のClover Hillでも、脳科学の研究と教育現場のデータを交えてそろばんとの相性を解説されています。
また、「IT業界の優秀な人材が集まる“シリコンバレー”には、約半数が発達特性の傾向があるとも言われる」という記事もあります。
引用:atGP
習い事① そろばん|見て・触って感覚で理解できる学習法
そろばんは、目で見て、手を使って数を動かすことで、自然に計算の感覚が身につく習い事です。
グレーゾーンの子どもに多い、
- 決まった手順に安心感を持つ「こだわりの強い」特性
- グループ活動よりも一人で集中しやすい傾向
- 音や視覚など外部刺激に敏感で、集中が切れやすいタイプ
にとっても、そろばんは合いやすい習い事です。
ルールが明確で、静かな環境で黙々と手元に集中できるので、外部刺激の少ない落ち着いた学習スタイルが確保できます。
さらに、上達のステップが数字で見える=達成感を感じやすいのもポイント。

「できた!」「前より速くなった!」といった小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感を育てやすいのも大きな魅力ですね。
👉 発達特性のある子どもにも、そろばんを教えている講師にインタビューしました。
授業中に落ち着きがなかった子が、そろばんを通じて変化していった実例も紹介。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
習い事② プログラミング|遊び感覚で論理的思考を伸ばす
もうひとつのおすすめは、プログラミング学習です。
といっても、難しいコードを書くわけではありません。
今は、キャラクターを動かしたり、簡単なゲームを作る感覚で楽しく学べる教材がたくさんあります。
画面上で「こう動かしたい」と思ったとおりにプログラムを組み立てることで、論理的に考える力が自然と育っていきます。
発達障害の子どもは、「自分のペースで進められること」「すぐに結果が見えること」に安心感を持つ傾向があるため、一人で黙々と取り組めるプログラミングは、まさにぴったりな学習方法です。

自分のペースで楽しく学べるプログラミングは、発達障害の子にも無理なく続けやすい習い事です。
「できた!」を実感しやすく、自己肯定感が上がる習い事の特徴
そろばんもプログラミングも、「目で見える成果」「はっきりしたゴール」があるのが特徴です。
これらは、グレーゾーンの子が特に苦手としがちな「曖昧な指示」や「終わりの見えない勉強」に比べて、達成感を得やすく、続けやすいというメリットがあります。
- できることがある
- 自分にも得意なことがある
という実感は、子どもの自信ややる気を引き出す大きな力になります。

目に見える成果があることで、「自分にもできる!」という自信が育ち、勉強が前向きになります。
そろばんやプログラミング以外の、グレーゾーン傾向の子に合う習い事をまとめた記事はこちら。
子どもによって違う「適した習い事・学び方」
「この子にはこの教材がいい」と一概に言えるものはありません。
子どもによって「理解しやすい方法」「頭に入りやすいスタイル」はそれぞれ違います。
ここでは、お子さんに合った学び方を見つけるヒントを3つの視点からお伝えします。
視覚優位・聴覚優位など特性に合わせた習い事選び
人にはそれぞれ、情報の理解しやすさや、考え方のクセに違いがあります。
これは正常な大人にもあるので安心してください。
よく知られているのが、
- 目で見て覚えるのが得意な「視覚優位」
- 聞いて覚えるのが得意な「聴覚優位」
たとえば――
- 図や絵のほうが理解しやすい → 視覚優位
- 音や話で覚えるのが得意 → 聴覚優位
最近では、思考のタイプにも注目されています。
- イメージで考える「ビジュアルシンカー」
- 言葉で考える「言語思考タイプ」
発達障害やグレーゾーンの子は、こうした特性が強く出ることがあり、合わない学習方法では理解が難しくなる場合があります。
まずは、
- 視覚・聴覚どちらが得意か?
- イメージ型か言葉型か?
を観察してみてください。
子どもに合った学び方に少し変えるだけで、理解がぐんと深まることがあります。
ワークより実体験・イメージ重視の習い事が合う場合
テキストを読んだり、何度も書いて覚えるといった学習は、合わない子にはストレスになりやすいです。
たとえば――
- 時計の読み方を紙で学ぶより、実物の時計で動かしてみる
- 計算を数字だけで練習するより、実際にお菓子を使って数える
- 理科の「浮く・沈む」を文章で読ませるより、実験して見せる
このように、実際に目で見て、体験して学ぶ方法の方が頭に入りやすい子もたくさんいます。

何度も反復するよりも、「これはこうなるんだ」と納得できるイメージを持てると記憶に残りやすいですよね。
音読よりアプリなど学び方を工夫できる習い事
昔ながらの紙のドリルや音読だけでは合わない場合、学び方そのものを変えてみるのも効果的です。
たとえば――
- 文字より絵が得意な子には「図解の多い教材」
- 書くことが苦手な子には「タブレットで、なぞり練習」
- 音読が苦手な子には「音声付きの学習アプリ」
こうした工夫は、学びへのハードルを下げ、「やってみたい」「わかった!」という気持ちを引き出すことに繋がります。
「教材を変える」「教え方を変える」ことは、特別なことではなく、お子さんにとって自然な道を見つけてあげるということです。

学習の“形”はひとつじゃない、という気持ちで柔軟に取り組んでみませんか?
家庭でできる発達障害の子どもへの学習・習い事サポート
「特別な教材や設備がないと無理…」と思われるかもしれませんが、家庭でできるサポートは意外とシンプルで効果的なことばかりです。
ここでは、よくある3つの困りごとに対して、今日からすぐに実践できるサポート法をご紹介します。
集中力が続かない子への「時間管理」と「環境づくり」
グレーゾーンの子どもは、じっと座って何十分も勉強を続けるのが苦手なことが多いです。
無理に続けさせると、イライラや癇癪につながってしまうことも。
そんなときは、「15分だけやろう」と時間を区切ってあげるのがおすすめです。
タイマーを使って「ピピッと鳴るまで集中しようね」と決めると、ゴールが見えるので取り組みやすくなります。
また、勉強する場所を工夫することも大切です。
たとえば、
- テレビの音がしない静かな場所
- 必要なものだけを置いたスッキリした机
- 明るい照明で集中しやすい空間
といった環境は、一般的に集中しやすいとされています。
ただし、全ての子どもに当てはまるわけではありません。
中には、
- 家族の気配があるリビングの方が安心できる子
- 壁に囲まれた狭い空間が落ち着く子
- いつもと違う場所でやるとやる気が出る子
もいます。
つまり、集中できる場所も子どもによって違います。

いろいろ試しながら、その子に合った“学びの空間”を見つけることが大切ですね。
「できた」を実感できる習い事や仕組みを取り入れる
発達特性やグレーゾーンの子どもは、結果が見えない学習や、ゴールが遠すぎる課題にモチベーションを失いやすい傾向があります。
だからこそ、「できた!」という成功体験を日常的に積み重ねてあげることがポイントです。
たとえば――
- 宿題が3ページなら「今日は1ページできたらOK!」
- 計算ドリル10問中5問できたら、シールを1枚貼る
- できたら「カレンダーに〇をつける」など、目に見える形で成果を残す
こうした仕組みがあると、子どもは「次もがんばろう」と自然に前向きになれます。

勉強を「苦手な時間」ではなく、「ちょっと嬉しい時間」に変える工夫が、学びの第一歩ですね。
発達障害やグレーゾーンの子どもが勉強につまずきやすい理由
「そろばん」や「プログラミング」が合う理由をもっと深く理解するために、ここでは、グレーゾーンの子どもがどうして学校の勉強につまずきやすいのかを見ていきましょう。
見た目では気づかれにくい学習の壁
グレーゾーンの子どもは、普段の会話や生活ではまったく問題がないように見えることが多いです。
だからこそ、まわりから「普通にできるはず」と思われやすく、勉強ができない=サボっている、やる気がないと誤解されてしまうことがあります。
でも実際は、
- 黒板の文字をノートに写すのが遅い
- 話を聞いていても頭に入りづらい
- 一度に複数のことを指示されると混乱する
など、表には見えにくい学習のハードルを抱えているケースがよくあります。
「見えない困りごと」を周囲が気づきにくいことが、つまずきの原因のひとつです。

一見わかりにくい困りごとが、子どもをつまずかせている原因になっていることもあります。
やる気の問題ではなく「学び方のミスマッチ」
子どもが勉強に集中できないと、「やる気が足りないのでは?」と思ってしまいがちですが、多くの場合、その子にとって“やりやすい方法”になっていないだけです。
たとえば、聞いて覚えるのが苦手な子にとっては、先生の説明が早すぎたり、文字だけの教材は理解が難しく感じます。
「やろうとしているのに、うまくできない」という状態が続くと、子どもは自信をなくし、やる気も失っていってしまいます。
だからこそ、その子に合った学び方=“合う勉強”を見つけてあげることがとても大切なんです。

一見わかりにくい困りごとが、子どもをつまずかせている原因になっていることもあります。
発達障害の子どもを家庭でサポートする3つのアプローチ
「子どもに合う勉強法があるのはわかった。でも、家庭ではどうサポートしたらいいの?」
そんなふうに悩んでいる方も多いかもしれません。
ここでは、筆者自身の経験の中から、比較的うまくいきやすかったと感じた3つの関わり方をご紹介します。
もちろん、子どもによって特性や感じ方はさまざまですので、すべてのご家庭に当てはまるわけではありません。
あくまでも一つの参考例として、試してみてくださいね。
得意・不得意を観察して習い事や学び方を選ぶ
まずは、お子さんの「できること」と「苦手なこと」にしっかり目を向けてみましょう。
たとえば――
- 絵を描くのは好きだけど、文字を読むのは苦手
- 暗記は苦手でも、考える力や想像力はすごい
- 一人で集中するのは得意だけど、大勢の中では混乱しやすい
こんなふうに、子どもの行動をよく観察すると、意外な“強み”が見えてくることがあります。
「何が得意なのか?」「どんな時にスムーズにできているか?」を知ることは、その子に合った学び方を探すヒントになります。
たとえば――
- 絵が好きな子には、図やイラストを使った教材が合うかも!
- 暗記が苦手な子には、ストーリー仕立ての問題や体験を通じた学びが効果的!
- 集中できる時間が短い子には、勉強時間を10分ずつで区切る方法もおすすめ!
このように、得意や苦手を理解することで、「どう教えればよいか」「どんな教材が向いているか」など、勉強に活かせる工夫が自然と見えてきます。

子どもの得意と苦手に気づくことで、その子に合った教え方や学び方が見えてきますよ。
否定しない声かけで安心して学べる環境を作る
子どもが間違えたり、うまくできなかったときに、「どうしてできないの?」「また忘れたの?」と否定するような言葉を使っていませんか?
その一言が、子どもの心を閉じてしまうこともあります。
たとえば――
- 「ここまでできたの、すごいね!」
- 「前よりも上手になってるよ!」
- 「苦手なことにチャレンジしたの、えらいね」
こうしたポジティブな声かけを続けることで、子どもは「自分は大丈夫」「がんばっていいんだ」と安心して取り組めるようになります。
無理に標準ペースに合わせない習い事選び
他の子と比べて、「なんでうちの子だけ…」と思うこともあるでしょう。
でも、すべての子どもが“同じペース”で学べるわけではありません。
学校のカリキュラムはあくまで目安。
標準に無理やり合わせようとすると、子どもも親も苦しくなってしまいます。
それよりも、
- 子どものペースで進める
- 得意なことから学ばせる
- 楽しめるやり方で試す
というように、「わが子に合ったやり方で学べばいい」という柔らかい姿勢で接することが、長い目で見て大きな安心と成長につながります。

「みんなと同じ」にこだわらず、わが子に合ったペースで学ぶことが、心の余裕と成長にもつながります。
まとめ|発達障害の子どもは「合う習い事」で大きく伸びる
グレーゾーンの子どもは、自分に合った方法で学べば、大きく力を伸ばせる可能性を持っています。
大切なのは、「みんなと同じやり方」にこだわるのではなく、「その子に合うやり方や得意を一緒に見つけること」。
そして、
- 「できた!」という達成感を少しずつ積み重ねること
- 周りと比べすぎず、わが子のペースを大切にすること
- 家庭・学校の力を借りながら、無理なく続けていくこと
これらが、子どもにとっての「学ぶ楽しさ」や「自己肯定感」につながっていきます。

「この子には、この子なりの輝き方がある」
大切なのは、その子のペースや特性に合った方法を見つけることですよ。
今回ご紹介したそろばんやプログラミングのように、「合う学習法や習い事」を見つけることで、子どもの表情や意欲が変わっていくことは本当に多いです。
冒頭でも紹介しましたが、
こだわりが強い子には、細かい操作を積み重ねていく「子ども向けプログラミング」がおすすめ。
自分のペースで進められて、思い通りに動かすために集中しやすく、達成感も得られやすいです。
感覚的や視覚的に理解が得意な子には、
「そろばん」のように目と手を使って学べる方法も効果的です。
繰り返しの動きが安心感につながり、集中力や数のイメージ力も育まれます。
どちらも、楽しみながら「できた!」を実感しやすく、勉強への自信や集中力にもつながります。